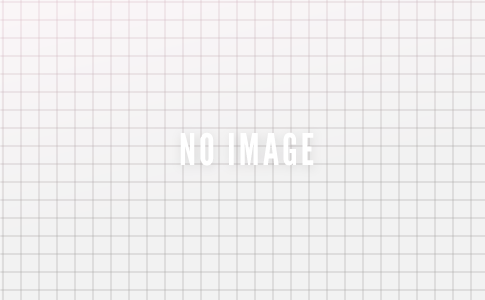「ボールをすぐに取られてしまう」
「パスを貰っても、次に何をすればいいかわからない」
「プレーの判断が遅い」
こんな悩みを抱えている方は、この記事で解決します。
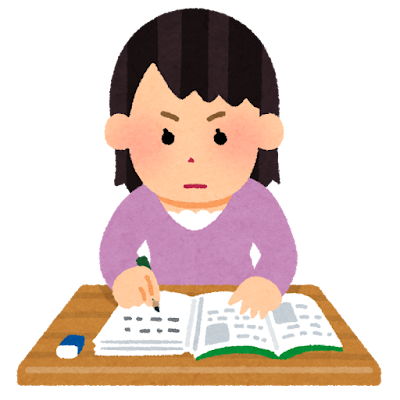
サッカーIQの高さとは、
「サッカーで勝つための戦略を知っているか」
「サッカーにおける有効な手法を知っているか」です。
つまり、暗記ゲー。知識量です。
シンプルに知らないだけ。
逆に、わかっているのに、守備をしない・動き出しをサボる、などは怒られて当然。
味方は、あなたがわかっていてサボっているのか、わからずにミスをしているのかは、知りません。なので、一緒くたにされて怒られます。
この記事を読めば、「次のプレーがわかる」「パスが来ても慌てない」「チャレンジしていい瞬間がわかる」「試合中疲れにくくなる」「サッカーIQが高い」状態になります。
元Jユースの僕が、すべてを教えます。
例えるなら、オセロ。
オセロって角を取った方が良いゲームですが、角を取った方が良いと知らず、自分の脳みそだけで考えてプレーして消耗。
角を取った方が良いと知るだけで、強くなる。
サッカーも同じ。
サッカーIQの高い人は、勝つ有効な手段を知っている。
サッカーIQを高めるには、まず土台の基礎知識が必要

サッカーIQを高める方法は、大きく2つあります。
- 試合映像を見る
- 書籍から学ぶ
ですが、その前にある程度の⓪基礎知識が必要になります。
⓪基礎知識は、僕がココで教えます。
記事後半で、『①映像分析・②書籍学習』についても触れます。⓪基礎知識がわかる方は、読み飛ばしてOKです。
では、いきます。
基礎知識⓪-1.サッカーは得失点差を競うスポーツである
まず、サッカーは得失点差を競うスポーツです。
初心者や下手なプレイヤーに多いのが、サッカーを「足でボールを上手く扱えるようにする競技」と勘違いしてしまうこと。
足元の技術があっても、失点をよくする、得点できない、ボールロストをする、のであればそれはサッカーが下手です。
ボールタッチが下手で、身体能力が低かったりしても、得点して失点しないプレーができていれば、それはサッカーが上手いです。
試合中はとにかく得点する・失点しないを念頭にプレーしましょう。
基礎知識⓪-2.攻守の優先順位を理解しよう
サッカーにおいて攻守には優先順位があります。
- ゴール(シュート)
- 裏(背後へ抜け出し)
- 縦(縦パス・楔のパス)
- 横(横パス・サイドチェンジ)
- 後(バックパス)
- インターセプト(パスカット)
- 前を向かせない(チェック・プレス)
- サイドを限定させる(ワンサイドカット)
- 遅らせる(ディレイ)
- シュートブロック(スライディング)
ひとつずつ解説すると、とてつもない量になるので、詳しくは別の記事にて解説します。
今回は、なんとなく頭の片隅に置いておいてくれればOKです。
基礎知識⓪-3.試合運び(フェーズ)を理解しよう
サッカーには、フェーズ・局面が存在します。
- ビルドアップ①
- ビルドアップ②
- 崩し
- フィニッシュ
基本的には、この流れで試合運び・フェーズというのは進行します。
①はGKを含むビルドアップ
②はGKを含まないビルドアップ
③は相手ゴールに近づく
④はシュートまで行く
その後、チームは、まずはハーフコートラインを超えたボールを保持を目指します。理由は、自陣ゴールから遠く、相手ゴールに近いから。失点のリスクを抑え、得点の可能性へ近づきます。
ハーフコートラインを超えてボール保持ができたら、崩しのターン。具体的には、ボックス内への侵入を目指します。ゴールに近いほど、シュートも決まりやすいからですね。
そして最後に、シュートで終わり。
これがサッカーのフェーズ・試合運びです。
基礎知識⓪-4.ハーフコートゲームを目指せ

サッカーは得失点差を競うスポーツだと、最初に解説しましたね。
繰り返しにはなりますが、
つまり、得点がしやすく・失点しにくいゲームをすれば良いということですが、すなわち、ハーフコートゲームです。
「ハーフコートゲーム」とは、敵陣地でボールを持ち、プレーし続けること。ハーフコートゲームをすると、相手はずっとゴール付近で守備することになるので、精神的・肉体的に、削られる。
自分たちからすると、自陣ゴールから遠いため失点のリスクが低く、相手ゴールに近いため、得点の機会が多くなります。気持ち的にも余裕を持ってプレーを続けられるので、精神的・肉体的にも疲労を感じにくくなります。
基礎知識⓪-5.ボックスに侵入しろ

ハーフコートゲームができたら、次は”崩し”のターン。
崩しとは、具体的に”ボックス内への侵入”を指します。
相手の守備をくぐりぬけ、ゴール前、すなわちボックス内侵入を目指します。ボックス内に侵入する理由は、得点により近づけるからです。
ゴールに近ければ近いほど、シュートは入りやすくなりますからね。
ボックス内に侵入する方法は、バイタルエリア侵入・クロス・アーリークロス・サイド攻撃・ドリブル単独突破などがあります。
基礎知識⓪-6.ボックス内に戦術は存在しない
ボックス内に侵入することができたら、あとは選手1人1人のアイデア・閃き・発想・感覚・経験になります。
すなわち、個の力です。
ボックス内では、戦術は意味をなしません。
監督の仕事は、ボックス内までボールを運ばせること。ボックス内までボールを運べたら、もう監督の力の及ぶ範囲ではありません。
ゴール前は人が密集しすぎているので、戦術的な崩しとか、ポジショニングができるとかいう次元ではないのです。
逆に、ゴール付近で崩そうとする方が難しくなります。
ゴール前で崩そうとして(シュートしないでパス)パスをすると大体失敗するのは、そういうことです。
⓪基礎知識まとめ|意識すべきはハーフコートゲームとボックス侵入

長かったと思いますが、読んでいただきありがとうございます。
お疲れ様です。
シンプルな内容だったと思いますが、知るだけでサッカーの見方・IQがかなり変わるはずです。
- ビルドアップ①
- ビルドアップ②
- 崩し
- フィニッシュ
おさらいしましょう。
サッカーには4フェーズ・試合運びがあり、試合中に意識すべきは2つ。「ハーフコートゲーム」と「ボックス侵入」。4局面を意識しなくても、この2つを意識していれば勝手に④フィニッシュまで達成される。
ここまでが、基礎。
これだけでも、十分ではありますすが、さらなるサッカーIQ向上のためには、試合映像の分析・書籍学習が確実に必要になってきます。
例を挙げると、ビルドアップしないショートカウンター・偽SB・偽9番・フォーメーションの相性や噛み合わせ…etc。
逆に、自陣へ敵を引き込み、相手が上がったところを、オフサイドにならないギリギリのタイミングで抜け出してカウンターを決める戦術もあります。
この場合、基礎基本のビルドアップは無視して、一気に局面をひっくり返して、崩しもほぼせずに、ボックス侵入・フィニッシュ到達を試みるわけです。
YouTubeの動画や書籍が難しく感じるのは、こういった応用知識のピースだけを解説しているから。でももう、この記事を読んだことで、応用知識も理解しやすくなったんじゃないかな。
ここから先は、さらに応用知識・サッカーIQを高める方法を、大きく2つにわけて紹介します。
サッカーIQを独学で高める方法は、大きく2つ【映像と書籍】

繰り返しにはなりますが、サッカーIQを独学で高める方法は、大きく2つ。
基礎知識を知った上で、
- 試合映像を見る
- 書籍から学ぶ
この2つに集約されます。
ここからは、映像分析でのポイント3つ、書籍で失敗したくない人向けに、僕が読んだ中から、質の高い・サッカーIQを高められる書籍紹介を6つをします。
サッカーIQを独学で高める方法①試合映像を見る
サッカーIQを独学で高める方法①は、試合映像を見ること。
ポイントは以下の3つ。
自身の試合映像を見る
プロの試合映像を見る
ハイライトではなくフルで見る
1つずつ、解説します。
ポイント①自身の試合映像を見る
なかなか自身の試合をビデオカメラで撮る機会は少ないですが、できるなら試合映像を撮影しましょう。見返すことで、「こんなにひどい動きだったのか…」「もうワンテンポはやくてもいいな」とか気付きを得られます。
強豪校、ユースチーム、運営がしっかりしているチームでは、試合映像の撮影がマストになっていたりもするので、移籍したり、最初にチーム選びをするのも1つ手です。
ポイント②プロの試合映像を見る

ポイント2つ目に、プロの試合影像は必ず見ましょう。
プロのゲームを『基礎知識①〜⑥』を理解した上で観戦すると、見える世界が、かなり大きく変わるはずです。
また、基礎基本・定石があるからこその、プロの裏をかくアイデアや応用的なプレーも多く発見できるでしょう。
多くのプレーを見て、知っているからこそ、実践でもアイデアが出てくるわけです。
例えるなら、料理をレシピだけ見て作ろうとする感じ。動画の方が絶対にわかりやすい。
料理のレシピはまだマシで、
例えば、ガラス職人になりたいあなたが、ガラスのコップを作ろうとするときに、紙面のマニュアルだけを見て作ろうとしている感じ。
映像を見た方がいいのはきっと伝わると思います。
ポイント③ハイライトではなくフルで見る

また、試合は必ず、ハイライトでなくフルで見ましょう。
ハイライトやプレー集は、試合の中のゴールやスーパープレイを切り抜いただけで、過程がすべてすっ飛ばされています。
ハイライトの切り取られた2~3分は盛り上がった所。ハイライトだけ見ていると、残りの87〜88分間のプレーの仕方がわからないはずです。
・勝ち点1(引き分けができればいい)試合の進め方。
・押し込まれてるときの、耐え方、悪い流れの変え方。
・試合序盤であっさり得点できちゃったあとの、気を引き締める声かけ。
こういったプレーは試合をフルで見ないと、学ぶことができません。
ハイライトの派手なプレーだけではなく、サッカーではシンプル・地味なプレーもたくさんあり、大事です。
ハイライトだけを見ているサッカー選手は、派手なプレーばかりをしがちになります。個人フットサルによくいますよね。最近サッカーを始めたタケシ君がドリブルばかりするのはそういうことです。
騙されたと思って、フルで試合映像を見てみてください。
点を取るまで、点を取ったあと、残り時間を逃げ切るためのプレーなど、90分間の戦い方を知ることで、よりサッカーIQが高くなります。
海外・国内サッカーどちらでもかまわないので、ぜひフルで試合を見てください。絶対にあなたのためになります。
サッカーIQを独学で高める方法②書籍
サッカーの戦術書や雑誌は無数にありますが、中でも良質なものだけをピックアップします。
『〔メッセージ〕これからサッカーの独学をする人へ』でも解説しましたが、ジグソーパズルのイメージを大切にしてください。
それぞれの本が、どのフェーズ・局面について解説しているピースなのか、意識して読むだけで、爆発的にサッカーIQ向上が期待できます。
おすすめサッカー書籍①サッカークリニック
1つ目は、大手ベースボール・マガジン社から毎月発刊される雑誌「サッカークリニック」です。
サッカー戦術について取り上げている雑誌です。
毎月一つの題材について触れていき、1年を通して読むとサッカーIQが向上する、というものです。一冊なんと約1000円。
また、毎年購入するとわかるのですが、だいたい同じ内容を1年間でループさせています。(9月はポゼッション、10月は1stタッチ…みたいな。)
なので、12冊(かなり薄い)を目標に、モチベーションを立てやすいことも選出の決め手。人間、ゴールが見えないとやる気も起きにくいですから。
また、過去1年分12冊をまとめて購入することもでき、1年も待つ必要がないのもポイント。
まずは一冊、お好きな内容のものから読んでみるのをおすすめします。
おすすめサッカー書籍②フットボールネーション
おすすめサッカー書籍2つ目は、フットボールネーションです。
「マンガでいいのか?」と思われがちですが、めちゃくちゃ内容が良い・濃い・実践的です。
サッカー先進国が、どんなトレーニング・育成をしているのか?などが全て詰まっています。
しかも普通にマンガとしてめちゃくちゃ面白いので、ガチでおすすめです。
おすすめサッカー書籍③相手を見てサッカーをする
おすすめサッカー書籍3つ目は、相手を見てサッカーをする。
サッカーというスポーツを、プロの観点から見るような書籍です。
例えるなら「監督の脳内」。
著者の岩政大樹さんは、元プロサッカー選手。日本代表のCBとしても選出されていたレジェンドです。
この書籍の内容は、「サイドバック」「センターバック」「ボランチ」「サイドハーフ」「トップ下」「フォワード」の全てのポジショニングの解説。主要システム解説(442、4231、4141、433…など)、メンタルや立ち位置、ゴール前の駆け引きなども解説されています。
まさに、サッカーの基礎がすべて濃縮され詰まった1冊。
「自伝」や「ドリブルスキル雑誌」もいいですが、まずは基礎から読んでみると、サッカーが上達するでしょう。
おすすめサッカー書籍④各種ポジション講座
こちらは、古くからある老舗本。
センターバック専門講座、ボランチ専門講座、ゴールキーパー専門講座、などがあります。
YouTubeやウェブサイトで無料で学べますが、千円払うだけで、より確実なプロの知識・考えが手に入る。そんなポジションごとの書籍です。
最近では販売されなくなってしまい、ちょっとレアな書籍です。
おすすめサッカー書籍⑤ドリブルデザイン
個サル・即席チーム・サイドアタッカーで、活躍したい人におすすめが「ドリブルデザイン」です。
YouTubeで神がかったドリブル動画をあげ、有名になった元フットサル選手「岡部将和」さんが執筆した、「ドリブル理論・研究の全て」が詰まっている一冊です。
『ドリブルは感覚』だと思っていた人は、絶対に読んでください。
読むだけで考えが変わり、「抜けるドリブルができる・わかる」ようになるのです。堂安律選手や原口元気選手も、岡部さんにドリブルの個人レッスンを依頼するほどの実績。
〔メッセージ〕これからサッカーの独学をする人へ
これから独学をする人は、順番を意識し、ジグソーパズルをしている気持ちで取り組む必要があります。
全てを順番通りに教えてくれるメディア・人間・コンテンツはおそらくありません。
具体的には、以下の順で試合は進みますが、
①ゴール>②ボックス侵入>③バイタル侵入・サイド攻撃>④ハーフコートゲーム・ビルドアップ
『ポケットの攻略法』という書籍があるなら、それは②のボックス内について詳しく書かれたパズルのピースであるということ。
監督や解説者が今言っていた内容は、どの状況・フェーズのことなのか?この書籍に書かれている内容は、ゴールから何歩前のプレーの話なのか?これらを意識するようにしてください。
サッカーIQを独学で高める方法2つ【まとめ】

サッカーIQを高める方法は、大きく2つ。
- 映像分析
- 書籍学習
①映像分析のコツは3つあり、
- 自身の試合映像を見ること
- プロの試合映像を見ること
- ハイライトではなくフルで試合を見ること
料理のように、レシピ本より、動画の方がイメージしやすいし、アマチュアの試合より、プロのお手本をたくさん見て記憶した方が良いから。
ハイライトは試合の盛り上がったところだけで、地味なプレーも大切だから。
→ハイライトだけを見る選手は、派手なプレーやドリブルしかしなくなる。
②書籍学習でおすすめな本は5つ
- サッカークリニック
- フットボールネーション
- 相手を見てサッカーをする
- 各ポジション専門講座
- ドリブルデザイン
宣伝
最後に、宣伝させてください。
Jユースクラブ・都1部の大学サッカー部にいた経験から、常識とはちょっと違う”サッカーの上手くなる方法”を書きました。
より実践的に、サッカーが上手くなる方法を解説しています。